通販レコード・新着盤
2020年03月13日
「変わり者」はいじめられるが 「別格の天才」はなにも気にしない
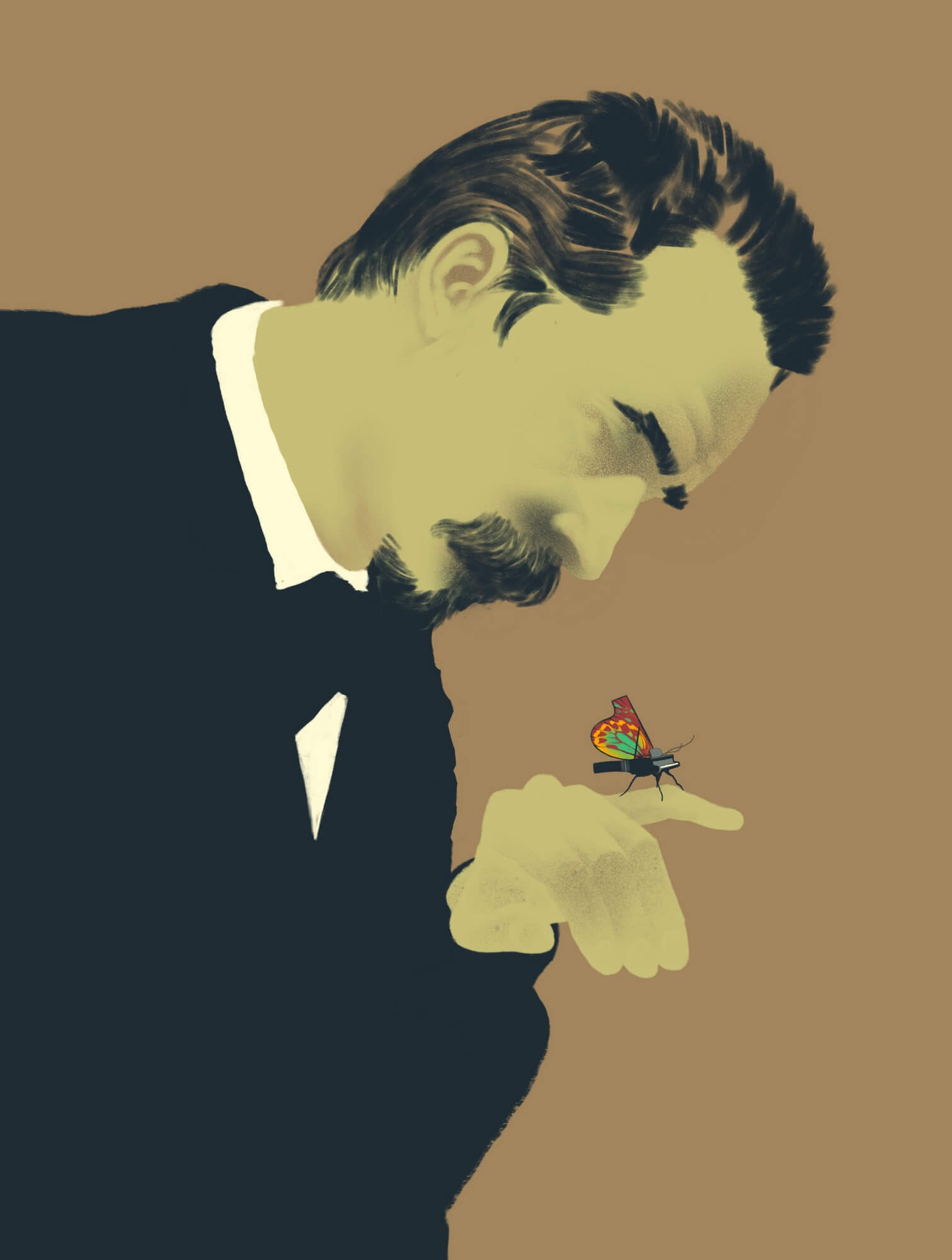
日本ではドイツ・リートの愛好者ではないと、馴染みのないフーゴ・ヴォルフ(Hugo Wolf, 1860.3.13〜1903.2.22)ですが、レコード、CD、そして配信でと、世界中でクラシック音楽が「メディア(録音物)」として聴かれるようになったのは、彼に心強い愛好者がいたから。その、生え抜きだったのがヴォルフ協会盤に結実する、やがてイギリスEMIの敏腕プロデューサーになる、ウォルター・レッグの存在。レッグはどうしても、ヴォルフの歌曲をレコード録音したかった。レコードがビジネスになるか闇の中だった大正時代の終わりに、制作資金を世界中に呼びかける、会員制の予約システムをはじめて行って、世界で最初のレコードを発売します。
ヴォルフは気難しく、相当な神経質だった。音楽以外の才能はなかったらしく、ウィーン音楽院に入る前の学校生活は浮いた存在で、彼の能力を発揮できるウィーン音楽院に入学したものの、教授のお仕着せがつまらなくって、少ししか勉強せず、いたずらで校長宛に脅迫状を送り退学処分。彼の繊細で神経質な性格は、いひゅもっこすで。ヴォルフが自分の作品を携えてブラームスを訪ねた時に、「もっと音楽の世界を広げた方がよい」と助言をもらった。また、ベートーヴェンの作品を研究していたグスタフ・ノッテボームの下で、対位法に習熟するためのレッスンを受けるべきとも言われた。それが自分への批判のように聞こえたため、ワーグナー派とブラームス派との対立に便乗する形となった。「うつ」の症状で投身自殺を図って未遂、救出後完全な狂人になって43歳直前に逝去してしまう。
それでも、歌曲の面で多くの実績を残した。人物はどうだったかではなく、その歌曲が素晴らしく、予約販売には日本から多くの募られて、歌曲全集のめどは余裕を得たほどです。その成果あってこそ、続くベートーヴェンのピアノ・ソナタ全曲録音、これはSPレコード100枚組を越えるもの。しかも、演奏者にシュナーベルを呼ぶほど資金繰りのよいものでした。
ヴァーグナーとかドビュッシーのような人たちは、革命家をもって目され、さまざまな人びとの情念を解放したのに反し、ヴァーグナーの赫々たる栄光のもとに生活してはいたものの、ブラームス(1833〜97)はその個性をほとんど無傷のまま守りつづけるのに成功した。当時のヨーロッパがあげて劇音楽に熱中していたにもかかわらず、ブラームスは、劇場のためには一指も染めないというくらい、その信念を押しとおした。
ブラームスは、偉大な古典派の最後の人だ、と言われたが、これは正確な言い方ではない。永遠のクラシシスムというものがあうのだ。しかし、リヒャルト・シュトラウス(1864〜1949)がドイツロマン派の最後の大家だというのは、それよりは正しい言い方といえよう。ブラームスとは正反対の精神から、オーストリアのオルガニスト、アントン・ブルックナー(1824〜96)は長大な交響曲を書いた。
日本は明治の初めに、西欧の技術知識を輸入し、文化芸術についても西洋から教師を招いて青年に学ばせた。時代はまだ後期ロマン派全盛である。その中心は、ドイツそして東欧やロシアでも民族派が台頭している。フランス音楽はややマンネリで退潮気味だった。そこで、やっぱり音楽はドイツだということになって、まじめな日本人はベートーヴェンを楽聖などと崇め、シューベルトやブラームスを西洋音楽の理想だと思ったのだろう。その頃、フランスでは印象派が登場しつつあったのだが、明治末期の日本人にはドビュッシーは前衛的過ぎた。
ヴォルフは気難しく、相当な神経質だった。音楽以外の才能はなかったらしく、ウィーン音楽院に入る前の学校生活は浮いた存在で、彼の能力を発揮できるウィーン音楽院に入学したものの、教授のお仕着せがつまらなくって、少ししか勉強せず、いたずらで校長宛に脅迫状を送り退学処分。彼の繊細で神経質な性格は、いひゅもっこすで。ヴォルフが自分の作品を携えてブラームスを訪ねた時に、「もっと音楽の世界を広げた方がよい」と助言をもらった。また、ベートーヴェンの作品を研究していたグスタフ・ノッテボームの下で、対位法に習熟するためのレッスンを受けるべきとも言われた。それが自分への批判のように聞こえたため、ワーグナー派とブラームス派との対立に便乗する形となった。「うつ」の症状で投身自殺を図って未遂、救出後完全な狂人になって43歳直前に逝去してしまう。
それでも、歌曲の面で多くの実績を残した。人物はどうだったかではなく、その歌曲が素晴らしく、予約販売には日本から多くの募られて、歌曲全集のめどは余裕を得たほどです。その成果あってこそ、続くベートーヴェンのピアノ・ソナタ全曲録音、これはSPレコード100枚組を越えるもの。しかも、演奏者にシュナーベルを呼ぶほど資金繰りのよいものでした。
ヴァーグナーとかドビュッシーのような人たちは、革命家をもって目され、さまざまな人びとの情念を解放したのに反し、ヴァーグナーの赫々たる栄光のもとに生活してはいたものの、ブラームス(1833〜97)はその個性をほとんど無傷のまま守りつづけるのに成功した。当時のヨーロッパがあげて劇音楽に熱中していたにもかかわらず、ブラームスは、劇場のためには一指も染めないというくらい、その信念を押しとおした。
ブラームスは、偉大な古典派の最後の人だ、と言われたが、これは正確な言い方ではない。永遠のクラシシスムというものがあうのだ。しかし、リヒャルト・シュトラウス(1864〜1949)がドイツロマン派の最後の大家だというのは、それよりは正しい言い方といえよう。ブラームスとは正反対の精神から、オーストリアのオルガニスト、アントン・ブルックナー(1824〜96)は長大な交響曲を書いた。
日本は明治の初めに、西欧の技術知識を輸入し、文化芸術についても西洋から教師を招いて青年に学ばせた。時代はまだ後期ロマン派全盛である。その中心は、ドイツそして東欧やロシアでも民族派が台頭している。フランス音楽はややマンネリで退潮気味だった。そこで、やっぱり音楽はドイツだということになって、まじめな日本人はベートーヴェンを楽聖などと崇め、シューベルトやブラームスを西洋音楽の理想だと思ったのだろう。その頃、フランスでは印象派が登場しつつあったのだが、明治末期の日本人にはドビュッシーは前衛的過ぎた。
Posted by analogsound at 23:35
Comments(0)
Comments(0)














