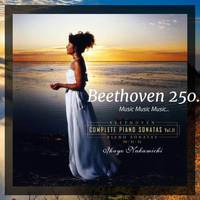通販レコード・新着盤
2020年10月03日
友人を思い出しながら作曲、、、「暁」という名がふさわしいベートーヴェンのピアノ・ソナタの超大作をを聴き比べる。

クラウディオ・アラウ
リズムとテンポが刻まれているところに、シューベルトの歌謡性とは違うグレン・グールドの鼻歌のようなフレーズが絡む。クラウディオ・アラウの演奏からは、映像が浮かんでくる。スリリングなものでも、推進するものでもない。アームチェア・ディテクティブで語られるような音楽だ。
ヴァレンティーナ・リシッツァ
ヴァレンティーナ・リシッツァの演奏はリズムを正確に守って、右手の旋律が添えられています。ベートーヴェンがクラシック音楽に持ち込んだ斬新な試みは《リズム》だと言うことは、最近クローズアップして説明される勘所です。この《ヴァルトシュタイン》ソナタから新しいピアノ音楽がスタートしたとも言われていること、シューベルトが影響を受けているのがよく感じ取れます。
ウラディーミル・アシュケナージ
通常「ワルトシュタイン・ソナタ」と呼ばれることの多いこの曲は、最終第3楽章のパッセージが、まばゆい太陽が朝上ってゆく様子にたとえられて、「オーロール(暁の)・ソナタ」とフランスやロシアで呼ばれています。難聴という音楽家にとって致命的な病気を乗り越えたベートーヴェンにとっても、ピアノ音楽にとってもこの曲は「暁」という名がふさわしいといえましょう。ロシア系ピアニストの演奏からは、この「暁」が感じられまる共通性がありますが、アシュケナージの演奏をその参考とします。
エミール・ギレリス
鋼鉄のタッチと通称される完璧なテクニックに加えて甘さを控えた格調高い演奏設計で非常に評価が高いピアニスト、ギレリスの古典的解釈のベートーヴェンです。バロック時代のスカルラッティやバッハ、ロマン派のシューマンやブラームス、さらにはドビュッシーやバルトーク、プロコフィエフといった20世紀音楽に至るまで幅広いレパートリーを持っていた。プロコフィエフからはピアノ・ソナタ第8番を献呈され、1944年12月29日にはこの作品を初演してもいる。とりわけベートーヴェンの解釈と演奏においては、骨太で男性的な演奏で「ミスター・ベートーヴェン」と呼ばれるほどであった。ドイツ・グラモフォンレーベルにベートーヴェンのピアノ・ソナタの録音が進行中に死去しました。
アニー・フィッシャー
溌溂とした表現力と細部にわたる集中力で圧倒されるアニー・フィッシャーのベートーヴェン。戦後はブダペスト中心に活動したため、ほぼヨーロッパのみでしか演奏に触れられなかったにもかかわらず世界的に評価が高いピアニストのひとりです。戦中・戦後通しての王道、ベートーヴェンはこうでなくてはと自信に輝いている。ハンガリー生まれの名女流ピアニストで、8歳でベートーヴェンのピアノ協奏曲第1番を演奏したと伝えられている。リストに系譜が引き継がれたことを実感する、フィッシャーのベートーヴェンは造形が大きく、感傷性や曖昧さのかけらもありません。テンポは早目で、聴き手の気持ちを煽るようなボルテージの高さが独特。有名な『悲愴』『月光』『熱情』など、はじめて聴く作品のような新鮮さに満ち、また緩徐楽章での語り口の巧さに引き込まれます。正統派でありながら、こんなベートーヴェンは絶対に聴けません。
1923年にフランツ・リスト音楽院に入学し、アルノルド・セーケイとエルンスト・フォン・ドホナーニより受け継いだ知的な解釈に加えて、男性的な力強さにも不足しないフィッシャーの持ち味が、ここでは見事に結実しています。「ウィンナートーン」と呼ばれるベーゼンドルファーの深みある響きも、彼女の解釈に相応しい効果を上げており魅力的。
1923年にフランツ・リスト音楽院に入学し、アルノルド・セーケイとエルンスト・フォン・ドホナーニより受け継いだ知的な解釈に加えて、男性的な力強さにも不足しないフィッシャーの持ち味が、ここでは見事に結実しています。「ウィンナートーン」と呼ばれるベーゼンドルファーの深みある響きも、彼女の解釈に相応しい効果を上げており魅力的。
ダニエル・バレンボイム
ベートーヴェンのソナタに抱く、一般的なスタイルです。
アルフレッド・ブレンデル
幻想的なムードをまとった、大人のベートーヴェンです。
悲愴感に打ちひしがれながらも強く生き抜いていく ― 音楽史上初のタイトル付きソナタを聴き比べる。
戻ることのない終わり ― 演奏家の人生観を聴き比べているような、そこに楽しさを発見させてくれるソナタだ。
永遠なる母性を表す変イ長調 ― 後期3大ソナタの中で最もメジャーで芸術性と聴きやすさをあわせもったソナタを聴き比べる。
ベートーヴェンの『ゴルトベルク変奏曲』(?) ― ポリフォニーの音楽へ急接近する最後の3つのソナタを聴き比べる
古今のソナタの金字塔にして最高傑作 ― 忠実に再現するためには2種類のピアノをステージに並べないとならない。
静かで叙情的な旋律が印象的 ― 初めて「ハンマークラヴィーア」と表記された〝国民主義的な考えの現れ〟を聴き比べる。
戻ることのない終わり ― 演奏家の人生観を聴き比べているような、そこに楽しさを発見させてくれるソナタだ。
永遠なる母性を表す変イ長調 ― 後期3大ソナタの中で最もメジャーで芸術性と聴きやすさをあわせもったソナタを聴き比べる。
ベートーヴェンの『ゴルトベルク変奏曲』(?) ― ポリフォニーの音楽へ急接近する最後の3つのソナタを聴き比べる
古今のソナタの金字塔にして最高傑作 ― 忠実に再現するためには2種類のピアノをステージに並べないとならない。
静かで叙情的な旋律が印象的 ― 初めて「ハンマークラヴィーア」と表記された〝国民主義的な考えの現れ〟を聴き比べる。