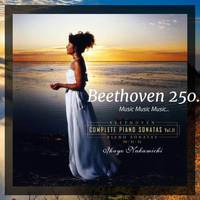通販レコード・新着盤
2020年10月18日
新型コロナ禍の不安と誹謗中傷のなかだから大切な人を想いながら聴いてみてはいかが ― 底知れぬ深みの間にある一輪の花
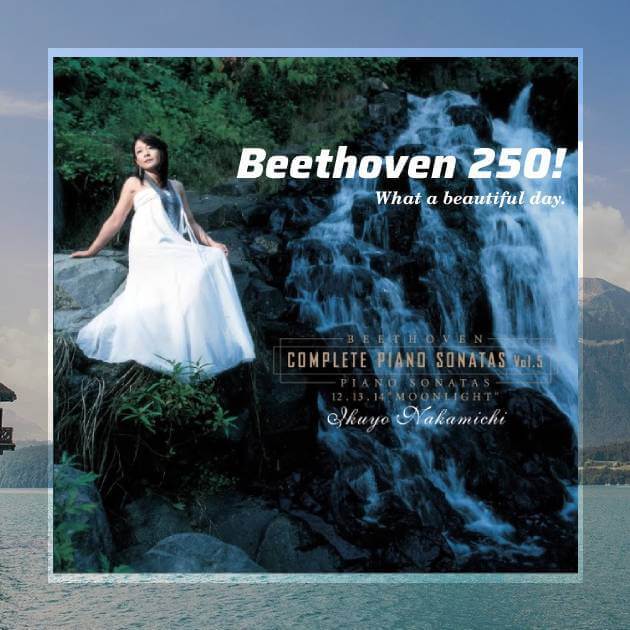
ベートーヴェンが恋心を抱いた少女に献呈
稲垣吾郎さんがベートーヴェンの好きな曲として31番のソナタを上げている。それは確かで、意見はない。傑作ソナタなら「熱情」「ハンマークラヴィーア」だろうが、《月光ソナタ》として親しまれてきたこの作品。ベートーヴェンのピアノ曲だとして、誰もが聴いたことがある曲に違いない。この《月光》というニックネームは、ベートーヴェンが付けたものではありません。ベートーヴェンの死後1832年に詩人のルートヴィヒ・レルシュタープが、このソナタに寄せたコメントから広まったものだそうです。
月光の名前の由来は、詩人レルシュタープが「このソナタの第1楽章はスイスの『四つの森の湖』にそそぐ月の光りを見るようだ」と形容したことから引用された命名で、まさにそれにふさわしい雰囲気を上手く云い当てたものです。
《2つの幻想曲風ソナタ》作品27の第1曲「第13番」にはソナタ形式の楽章が1つもなく、また、楽章間を切れめなく演奏するようにという指示が書かれていました。終楽章に比重が置かれるという構成は、この『月光ソナタ』でより一層発展していきます。
1802年3月に出版する「嬰ハ短調」ソナタ《2つの幻想曲風ソナタ》作品27の第2曲、《月光ソナタ》を献呈したのがベートーヴェンの弟子であり恋人でもあったといわれる14歳年下の伯爵令嬢ジュリエッタ・グイッチャルディであった。ベートーヴェン自身はソナタ形式ではなく、幻想曲的手法をとっている。
曲は3楽章からなり、第1楽章は3連符の神秘的で幻想的な分散和音から始まり、この序奏部が全体の性格を決定している。第2楽章はやすらぎの音楽などと解釈されるが、ベートーヴェンがここで意図したのはより新しい気分をもった音楽だった。ベートーヴェンは常に時代の先を読み、作品に斬新さを加えていったが、ここでも演奏家や聴き手の心を高揚させる新しい音楽を生み出している。リストはこれを「底知れぬ深みの間にある一輪の花」と称した。そして第3楽章は内容的に見てもピアニスティックな効果においても、この時点までに作曲されたベートーヴェンの作品のなかでもっとも充実した音楽となっている。第1主題ははげしく、第2主題は華麗な美しさが印象的だ。
このようにして、ベートーヴェンの創作が徐々に楽章形式の配置に変化を付けることから始まり、今度は楽章の内容について、更に検討して行くこととなったのは偶然ではなかったのです。
1800年にはブルンスヴィク姉妹とは従姉妹にあたるユリア(愛称ジュリエッタ)・グイッチャルディ(1784〜1856)が弟子入りする。
ベートーヴェンは一時期彼女に恋愛感情を抱いたことがあった。1801年11月16日付でヴェーゲラーに宛てた長い手紙(BB70)で持病の内臓と難聴の悩みを述べたあとに、「ひとりの愛すべき、夢のように魅惑的な少女が状況を一変させてくれたのだ、彼女は私を愛し、私も彼女を愛している。この2年間には幸せなことも時にはあったのだ。結婚が私に幸福をもたらしてくれるかもしれないと、初めて感じている」と述べている。
この少女が当時17歳のジュリエッタ・グイッチャルディである。もちろんベートーヴェンは身分の違いとはっきりと自覚しており、この結婚が実現するとは考えていなかったが、ジュリエッタにレッスンすることは、身体的な苦痛を抱えていたベートーヴェンの心をいくぶんか癒したのも確かだ。
ベートーヴェンの発想は、もともとモーツアルトのオペラ『ドン・ジョバンニ』のなかの、騎士長がドン・ジョバンニの剣に刺されて倒れて息が絶えてゆく劇的な場面の音楽からヒントを得て書かれた如く、全体は重苦しい深刻な気分の哀悼の音楽です。
このソナタは、全体の楽章構成を見てみると面白いことに気付きます。
第一楽章 Adagio sostenuto
第二楽章 Allegretto(Scherzo)
第三楽章 Presto agitato
となっていて、これは通常のピアノ・ソナタの第一楽章が省略されているということなのです。そのころのピアノ・ソナタの常識としては、このように遅い楽奏の楽章で始まるピアノ・ソナタというのはありませんでした。
この曲は、ベートーヴェンが恋心を抱いた少女ジュリエッタに献呈されました。静かな第1楽章から、激しさを増す第3楽章まで、大切な人を想いながら聴いてみてはいかがでしょうか。
悲愴感に打ちひしがれながらも強く生き抜いていく ― 音楽史上初のタイトル付きソナタを聴き比べる。
戻ることのない終わり ― 演奏家の人生観を聴き比べているような、そこに楽しさを発見させてくれるソナタだ。
永遠なる母性を表す変イ長調 ― 後期3大ソナタの中で最もメジャーで芸術性と聴きやすさをあわせもったソナタを聴き比べる。
ベートーヴェンの『ゴルトベルク変奏曲』(?) ― ポリフォニーの音楽へ急接近する最後の3つのソナタを聴き比べる
古今のソナタの金字塔にして最高傑作 ― 忠実に再現するためには2種類のピアノをステージに並べないとならない。
静かで叙情的な旋律が印象的 ― 初めて「ハンマークラヴィーア」と表記された〝国民主義的な考えの現れ〟を聴き比べる。
戻ることのない終わり ― 演奏家の人生観を聴き比べているような、そこに楽しさを発見させてくれるソナタだ。
永遠なる母性を表す変イ長調 ― 後期3大ソナタの中で最もメジャーで芸術性と聴きやすさをあわせもったソナタを聴き比べる。
ベートーヴェンの『ゴルトベルク変奏曲』(?) ― ポリフォニーの音楽へ急接近する最後の3つのソナタを聴き比べる
古今のソナタの金字塔にして最高傑作 ― 忠実に再現するためには2種類のピアノをステージに並べないとならない。
静かで叙情的な旋律が印象的 ― 初めて「ハンマークラヴィーア」と表記された〝国民主義的な考えの現れ〟を聴き比べる。