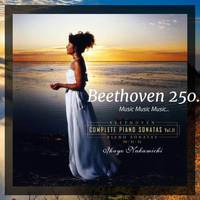通販レコード・新着盤
2020年10月19日
《田園》という名前の名曲が、ベートーヴェンにはもう一曲ある ― 楽聖の作曲様式を知る上で興味深いソナタを聴き比べる

交響曲第6番の《田園》と聴き比べてください
誕生祝いに頂いたオルゴール。将来の宝物がいっぱい詰まっているようにと、熊本の伝統工芸で作られた小箱のフタを開けるとオルゴールが鳴り出す仕組みだった。曲を選ぶのに親は考えたのかは、今でははっきりしないが『エリーゼのために』だった。〝ベートーベン〟の名が、最初に記憶した作曲家の名前だったのは明らかだ。
スヌーピーが好きになって、『ピーナッツ』を毎月定期購読するようになると、シュレーダーという名前の少年がベートーヴェンにぞっこんだった。
チャーリー、サリー、ルーシー、フリーダと古いアメリカ映画やテレビドラマでよく出てくる名前の登場人物たちの中で、シュレーダーという名前は記憶に残った。
スヌーピーやチャーリー・ブラウン達が活躍する「ピーナッツ」に登場する、トイピアノでベートーベンを演奏しちゃう男の子です。それってシュローダーでしょ?(Wikipediaを確認して)という人も少なくないと思いますが、当時はシュレーダーでした。「ムーミン」のスノークのお嬢さんもノンノンからフローレンに変わっててビックリしたけど、いつの間にシュローダーになったんだか。谷川俊太郎の訳でもシュレーダーだった。
映画「戦場のピアニスト」で主人公がシュピルマンとおどおど名前を答えると、ドイツ軍将校が、「ピアニストらしい名前だな」、と認めるやり取りがあるが、シュローダーの名前の元はそこらへんだろう。
閑話休題。《月光》はメロディーが覚えやすく、曲の構成もすぐに覚えた。その頃には、第2楽章も、第3楽章も、第1楽章以上に好きになっていた。センチメンタルを知るようになると、《悲愴》に魅了された。《熱情》はなかなかに骨が折れた。その《熱情》が突然きになる存在になって、毎日聴いているようになると、ベートーヴェンのソナタを本腰入れて聴いてみようと思い立った。そして最初に白羽の矢があたったのが、《田園》でした。それも偶然で、マウリツィオ・ポリーニのベートーヴェン・ソナタ全曲録音が、ちょうど《田園》に至ったときだったから。
同じ名前で親しまれている、交響曲第6番《田園》がありますが、こちらはベートーヴェン自身がつけたものではありません。1802年の初版譜にはついていません。しかし、のどかな風景が思い浮かぶような穏やかな作品です。
伝統的に田園的なものを描いた曲はへ長調か二長調で書かれていますし、冒頭の主音による保続音(ドローン)がミュゼット、もしくはバグパイプといった農民のための楽器を思わせるということがずっと言われてきました。《田園》というタイトルは1838年の出版譜からつけられるようになったもので、ハンブルクの出版社クランツが作曲者の死後1838年の出版時に『Sonate pastrale』と銘打ったのが最初とされる。名称が付された背景には、当時田園趣味の音楽が流行していたところを狙った商業的意図があるのではないかとする意見もあるが、いずれにせよこの愛称は楽曲の性格をうまく捉えており、今日まで残ったものと思われる。調性と楽器を模倣した主音保持がもたらす雰囲気は、確かに田園風景を感じさせてくれます。
攻めの〝op.27〟と打って変わって、この曲はソナタ形式による第1楽章をもつ伝統的な「4楽章ソナタ」形式で回顧的な趣の曲ですが、その中にはやはりベートーヴェンならではの革新性があります。
パストラル風の第2楽章が素朴で美しく、ベートーヴェンも好んで弾いていたそうです。そんな光景が浮かんでくるので、わたしは多くの音が頭の中いっぱいに溜まると、ここに戻ってリセットします。
悲愴感に打ちひしがれながらも強く生き抜いていく ― 音楽史上初のタイトル付きソナタを聴き比べる。
戻ることのない終わり ― 演奏家の人生観を聴き比べているような、そこに楽しさを発見させてくれるソナタだ。
永遠なる母性を表す変イ長調 ― 後期3大ソナタの中で最もメジャーで芸術性と聴きやすさをあわせもったソナタを聴き比べる。
ベートーヴェンの『ゴルトベルク変奏曲』(?) ― ポリフォニーの音楽へ急接近する最後の3つのソナタを聴き比べる
古今のソナタの金字塔にして最高傑作 ― 忠実に再現するためには2種類のピアノをステージに並べないとならない。
静かで叙情的な旋律が印象的 ― 初めて「ハンマークラヴィーア」と表記された〝国民主義的な考えの現れ〟を聴き比べる。
戻ることのない終わり ― 演奏家の人生観を聴き比べているような、そこに楽しさを発見させてくれるソナタだ。
永遠なる母性を表す変イ長調 ― 後期3大ソナタの中で最もメジャーで芸術性と聴きやすさをあわせもったソナタを聴き比べる。
ベートーヴェンの『ゴルトベルク変奏曲』(?) ― ポリフォニーの音楽へ急接近する最後の3つのソナタを聴き比べる
古今のソナタの金字塔にして最高傑作 ― 忠実に再現するためには2種類のピアノをステージに並べないとならない。
静かで叙情的な旋律が印象的 ― 初めて「ハンマークラヴィーア」と表記された〝国民主義的な考えの現れ〟を聴き比べる。