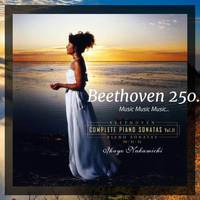通販レコード・新着盤
2020年10月21日
「芸術のために生きるのだ」というベートーヴェンの決意 ― 〝十字架の音形〟が頻繁に現れるテンペスト・ソナタを聴き比べる
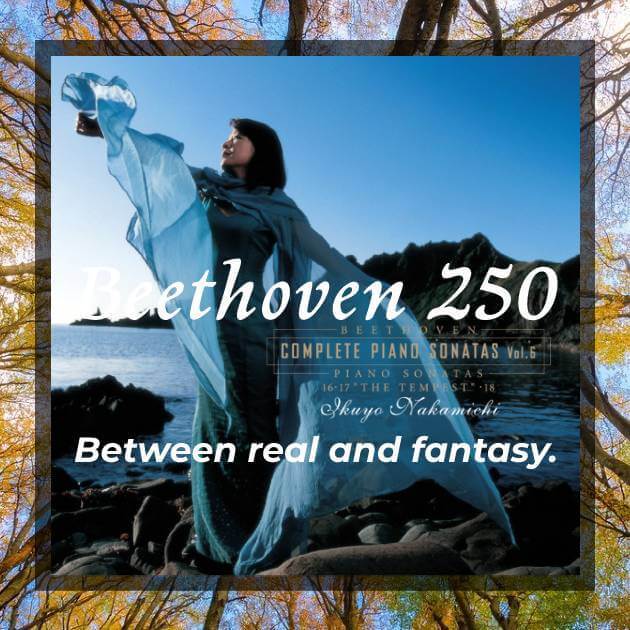
ピアノ音楽に劇的物語を盛り込んだ革新、頻繁に現れる〝十字架の音形〟
中学3年生の三学期にわたしは、シューベルトに没頭しました。日中はシューベルトの四重奏曲をBGMにし、夜はシューベルトの歌曲を白々と夜が明けるまで聞き入りました。彼の出口を求めるような音楽に共感するものを感じたのかもしれない。当時は気が付きませんでしたが、今振り返れば納得できそうです。「美しい水車屋の娘」の恋と失恋。そこからの逃亡と、さすらいの中にいる「冬の旅」。幻の太陽と、怖いものを告げるようなカラスの鳴き声。その後に在る「白鳥の歌」の透明さ。なのに捉えようのない形のないものが先にいるような音楽。
シューベルトの歌曲には一つ一つの物語が在る。それは大きな世界観を詰め込んだ箱庭の中にあるような物語。シューベルトはオペラを作曲していないのか。ベートーヴェンはオペラを「フィデリオ」ひとつしか書きませんでしたけれども、シューベルトは劇付随音楽はのこしていますが、オペラには何度もトライしたようで、未完成といっても断片だけが残っている。
シューベルトの歌曲を理解するためには、ヨーロッパの古い宗教観も理解しないといけないかもしれない。シューベルトがのこしたミサ曲は、予想していたより数多く残っている。それらをレコード店で見つけ出しては聴いていく過程で、モーツァルトのレクイエムの虜になった。
モーツァルトのレクイエムはニ短調。モーツァルトにト長調の曲は数多いが、ニ短調は特別な存在だったらしい。ベートーヴェンがカデンツァ(本来演奏者によって即興される部分)を作曲するほど好んだ、モーツァルトの「ピアノ協奏曲第20番 ニ短調」もそうだが、これを踏まえてベートーヴェンを聴くときも、ニ短調が気になる存在。
「3つのピアノ・ソナタ op.31」の2曲目。通称《テンペスト》と呼ばれるこの曲。ベートーヴェンの忠実な下僕とされている弟子のアントン・シンドラーが「この作品はどのように考えたらよいか」と作品の解釈をベートーヴェンに尋ねたところ、ベートーヴェンは面倒臭かったのか、「シェークスピアのテンペストを読め」と言ったという逸話から、この作品が『テンペスト』と呼ばれることとなりました。
ベートーヴェンにしてみれば、シントラーの世話焼きは時には非常に煩いものであったのでしょうが、このベートーヴェンの答えが、わたしたちの鑑賞のガイドラインになっているのは大変に有り難い。
第1楽章の冒頭の和音のアルペジオ。それは、弟アントニオによって君主の地位を横領され、娘ミランダと共に絶海の孤島に追放された王、プロスペローが海に面した岩壁に座して竪琴を奏で、我が身の不運を嘆いている情況を彷彿とさせる名場面です。
その後につづく第2主題にクロイツ音型(十字架音型)、「ラ-ソ♯-ラ-シ♭-ラ」が出てくる。最初と最後の音が同じ近接する4音の組み合わせによって、4つの分枝をもつ十字架を表していることからその名前がついているクロイツ(十字架)の音型は、バロック時代によく使われていました。ですからクロイツ音型の使用は特異な事ではないのですが、「ハイリゲンシュタットの遺書」の時期にこういう音型が使われているということは、そこにベートーヴェンは何某かの意味を込めていたのではないかと思えてしまうのです。
第2楽章にもターン(主要音を取り囲むように動く装飾音のかたちで、クロイツ音型が出てきます。第2楽章の譬え様もない美しさ、これはまさに娘ミランダの純真無垢な愛の世界、汚れを知らぬ天使の如き清らかな心を、ベートーヴェンは歌声によって現したものでしょう。
第3楽章の楽想は、復讐の嵐によって、弟アントニオ一行の乗っている舟を難破させ、 命からがら島にたどりついた彼らと対面するという、一大悲劇の場面を思い窺わせる音楽です。
この作品31-2『テンペスト』はベートーヴェンのピアノ音楽としても、作品に劇的物語を盛り込むという観点からみれば、知らず知らずのうちに後に出現するピアノ音楽の記念碑的な傑作『熱情ソナタ』への創作の伏線となりました。
悲愴感に打ちひしがれながらも強く生き抜いていく ― 音楽史上初のタイトル付きソナタを聴き比べる。
戻ることのない終わり ― 演奏家の人生観を聴き比べているような、そこに楽しさを発見させてくれるソナタだ。
永遠なる母性を表す変イ長調 ― 後期3大ソナタの中で最もメジャーで芸術性と聴きやすさをあわせもったソナタを聴き比べる。
ベートーヴェンの『ゴルトベルク変奏曲』(?) ― ポリフォニーの音楽へ急接近する最後の3つのソナタを聴き比べる
古今のソナタの金字塔にして最高傑作 ― 忠実に再現するためには2種類のピアノをステージに並べないとならない。
静かで叙情的な旋律が印象的 ― 初めて「ハンマークラヴィーア」と表記された〝国民主義的な考えの現れ〟を聴き比べる。
戻ることのない終わり ― 演奏家の人生観を聴き比べているような、そこに楽しさを発見させてくれるソナタだ。
永遠なる母性を表す変イ長調 ― 後期3大ソナタの中で最もメジャーで芸術性と聴きやすさをあわせもったソナタを聴き比べる。
ベートーヴェンの『ゴルトベルク変奏曲』(?) ― ポリフォニーの音楽へ急接近する最後の3つのソナタを聴き比べる
古今のソナタの金字塔にして最高傑作 ― 忠実に再現するためには2種類のピアノをステージに並べないとならない。
静かで叙情的な旋律が印象的 ― 初めて「ハンマークラヴィーア」と表記された〝国民主義的な考えの現れ〟を聴き比べる。