通販レコード・新着盤
2020年10月14日
ベートーヴェンの和声感覚は完全にロマン主義を先取りしていた ― 「新しいことを!」という強いメッセージを聴き比べる。
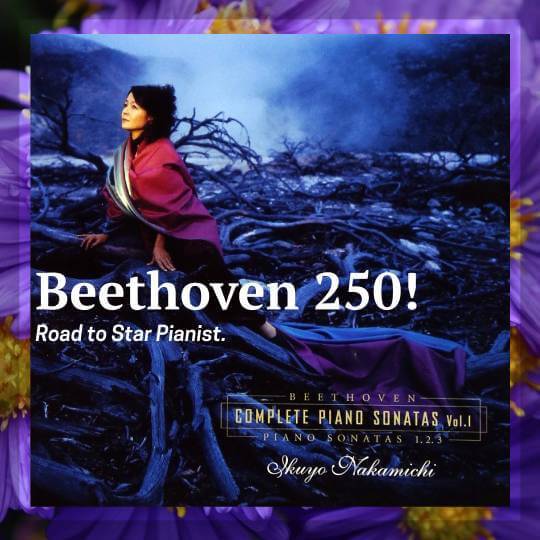
ベートーヴェンは、3つのピアノ・ソナタでロマン主義への道を示しました。のちの彼のピアノ・ソナタと聴き比べるのも面白いかもしれません。
ベートーヴェンの「新しいことを!」という強いメッセージが込められている「作品2」の3曲。「第1番」は調性、「第2番」は形式、「第3番」は特にベートーヴェンの独自性が表れていて、響きや規模、広い音域を駆け巡るオクターヴのパッセージなど、使われるテクニックは完全にピアノ協奏曲を想定しています。蓄えてきたテクニックを存分に発揮した、ピアノ協奏曲を思わせる巨大な書法と調の特殊性。ピアノソナタでありながら、極め付けにカデンツァも置かれています。さらに、主調がハ長調なのに、第2楽章をホ長調にするという当時の常識では考えられない調設定の特殊さも挙げられます。ベートーヴェンの和声感覚は完全にロマン主義を先取りしていたと言えるでしょう。
ベートーヴェンのピアノ・ソナタ32曲を作曲順に見ていくと、ベートーヴェンがどんどん新しい世界に突き進んでいくさまと、その素晴らしいメロディーメーカーぶりがわかってきます。
しかし今回は、「作品2」の3曲以前に作曲された、「19番」「20番」の〝やさしいソナタ〟。ベートーヴェンのピアノ作品の個性が楽しみやすい、〝ワルトシュタイン〟〝熱情〟を聴いたあと、モーツァルトやハイドンのバロック音楽をピアノの楽器としての発展に適応させながら昇華している「4番」から「10番」までを聴いて、そのうえで「作品2」に戻ってきました。
このことで、ベートーヴェンは最初からベートーヴェンの音楽を持っていたことがわかっていただけるでしょう。
明日聴き比べる「第11番」のソナタは「作品2」(第1〜3番)やOp7(第4番)のソナタでやってきたことの集大成のような位置づけにあると言ってもいい作品。ベートーヴェンの古典的なスタイルに対する考え方を統合し、総決算した作品です。いよいよベートーヴェンは「実験期」に入っていきます。














