通販レコード・新着盤
2020年10月16日
ソナタ形式の楽章をつかわない革新 ― この曲をもって、新たなステージに立ったベートーヴェンを聴き比べる。
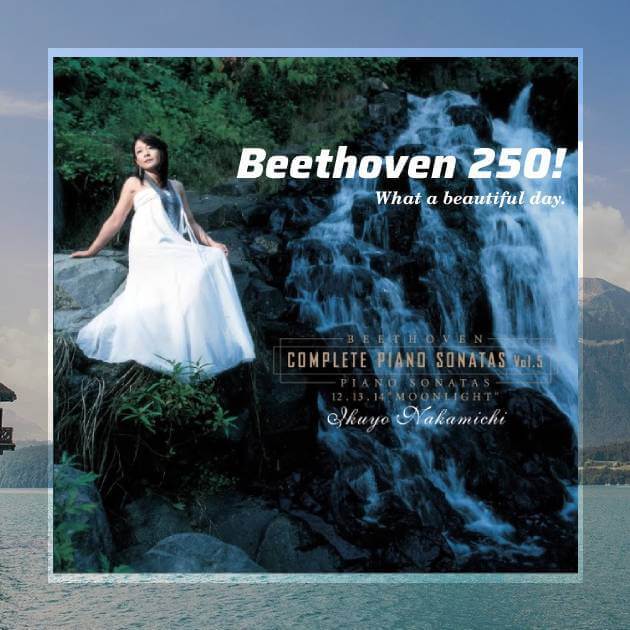
《葬送》の名をもつ革新的な作品
直前に書かれたという「ピアノ・ソナタ第11番 Op.22」と聴き比べると、革新的な部分をより感じられるかもしれません。1801年にはこのOp26を含めて、4曲のピアノ・ソナタが書かれており、どれも実験的な作品になっています。
この曲をもって、新たなステージに立ったベートーヴェン。これまでピアノ・ソナタで当たり前とされていた3楽章構成から脱却し、4楽章構成で作曲しています。いや4楽章構成をとっているということでは第2期の性格も受け継いでいるが、各楽章の構成は第2期とは全く異なる。
初めての交響曲や弦楽四重奏曲で大きな成功を収めることになるこの時期、ピアノ・ソナタではさらなる新しい表現様式を求めてさまざまな実験的革新が試みられる。この時期の最大の特徴はソナタ形式による第1楽章を回避することである。
《葬送》の愛称をもつこの作品、第1楽章が変奏曲、第2楽章がスケルツォ、第3楽章がマルチャ・フュネブレ(葬送行進曲)、そして終楽章がロンドとなっている。四楽章制ですが、ソナタ形式は1つもなく、続く『幻想風ソナタ』にむけて、古典的なソナタ形式からの脱却をはかっています。
第1楽章の変奏曲は、後期作品を思わせるような敬虔な曲調です。第3楽章が葬送行進曲なので、『葬送』という愛称で呼ばれています。ショパンはこの曲が好きで、コンサートで演奏することもあったそうです。














