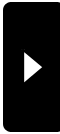通販レコード・新着盤
2020年10月11日
〝不思議な浮遊感〟が感じられる ― 全楽章を通して明るく、面白い、遊び心がたっぷり詰まったソナタを聴き比べる。
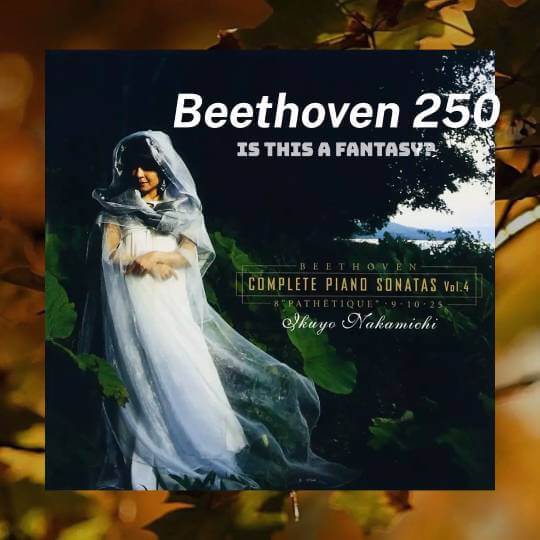
ソナタの中での初の変奏曲を選んだ第2楽章はオーケストラ的。作品14の2曲は今まで以上にピアノの表現を超えたところが多い。終楽章には「Scherzo」の指示がついているが、ロンド形式と言える内容で、この指示は音楽表情とか性格的な意味合いが強い。小節全体休止が3回出てきたり、唐突に違う音型が出てきたり、拍子を捉えづらいところに、不思議な浮遊感が生み出されていたり、消えるような終わり方も予想がつかない面白さです。
第3楽章の「スケルツォ」には、「冗談、ユーモア、ふざけた」といったような意味があります。遊び心がたっぷり詰まったピアノ・ソナタをぜひ聴いてみましょう。
2020年10月10日
ピアノの楽器としての将来性を確信したベートーヴェン ― チェンバロを切り捨てピアノのためだけに作曲した大曲を聴き比べる。
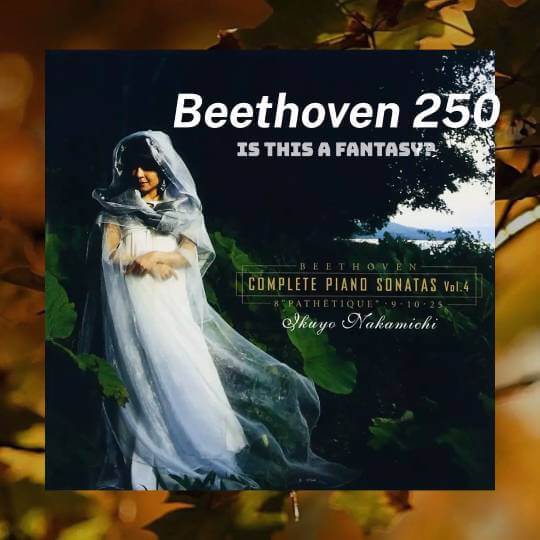
ピアノという楽器の進化とともにピアノ・ソナタを書き続けたベートーヴェン。《悲愴》くらいまでは、鍵盤楽器といえばチェンバロが主流でした。
「第9番」の頃はそろそろ19世紀になろうという時期で、ちょうど楽器が入れ替わる時期に差し掛かっていて、チェンバロよりもピアノフォルテが広く普及してきました。少しずつチェンバロ(あるいはクラヴサン)という表記が消えてゆく時代でした。
ベートーヴェンのピアノ作品も、《悲愴》までは「チェンバロまたはピアノフォルテのためのPour le Clavecin ou Piano-Forte」という記述がありましたが、「第9番」からは「ピアノフォルテのためのPour le Piano-Forte」となります。
出版社としては、2つの楽器で演奏可能とした方が売りやすかったでしょうが、のちに弦楽四重奏にも編曲される大曲第9番は、すぐに音が減衰してしまうチェンバロで弾くのは難しいフレーズが出てきます。ついに「ピアノだけ」を想定した作品となりました。
2020年10月09日
悲愴感に打ちひしがれながらも強く生き抜いていく ― 音楽史上初のタイトル付きソナタを聴き比べる。
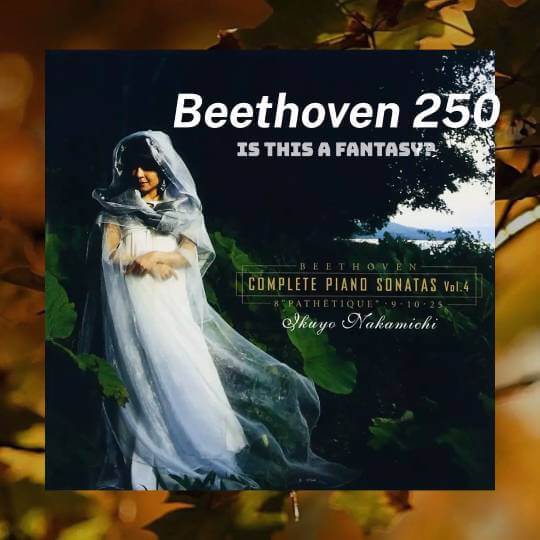
初版譜には「大ソナタ 悲愴 Grande Sonate pathétique」と書かれています。当時ピアノ・ソナタにタイトルをつけることはありませんでしたから、初めてのタイトル付きソナタと言えましょう。
ベートーヴェンがウィーンでピアニストとして成功しようと頑張りしすぎて、夏風邪がもとで難聴を患い。作曲家として進み始めた、1798年から1801年まで、ナポレオンが率いるフランス軍がエジプト・シリアへ遠征した。5万の兵が投入されたこの東方遠征には、151名もの民間知識人が同行していました。イギリスのインド航路を遮断すべくの遠征であった。戦果は散々だったけど、エジプト文明の発見という、人類としては大きな収穫を得ています。18世紀当時の調性格論に鑑みると、「悲愴」という言葉は、悲劇的なもの、というよりも情熱に近いのかもしれません、悲愴感に打ちひしがれながらも強く生き抜いていく、というエールが込められています。
自筆譜が紛失しているため、タイトルをベートーヴェン自身がつけたという証拠はないそうですが、初版譜の表紙に印刷されているということは、承認していたのは確かなようです。「ソナタにタイトルをつける」という史上初の試みまでやってのける。この点でも革新的なベートーヴェンです。
2020年10月08日
ピアニストから作曲家への過渡期に至り、響きも構成もオーケストラ作品。
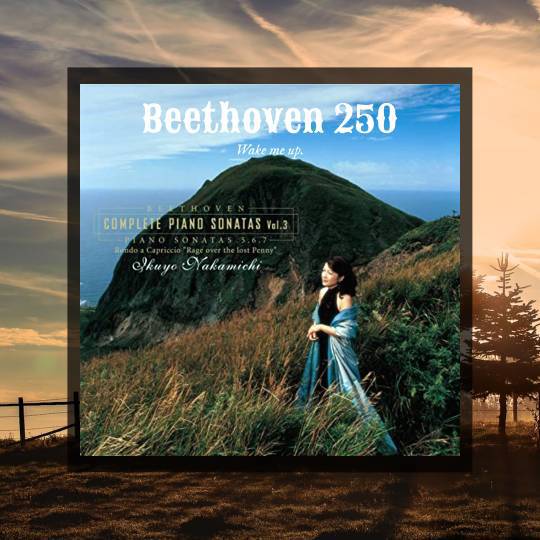
ベートーヴェンの自己の音楽追及の姿勢もプラハ ― ベルリン旅行以後大きく変わっていたが、作品発表の場は相変わらずリヒノウスキー侯邸での室内演奏会を中心とするものであった。
作品はこれまでのようなピアノ中心のものから、弦楽アンサンブルのような本格的室内楽へ傾斜する様子が窺える。しかし、1796年から翌97年にかけてはまだピアノ曲が多く、ピアノ・ソナタ作品7や「3つのピアノ・ソナタ」作品10、さらには初期の傑作ソナタとなる《悲愴ソナタ》作品13や作品14-1までの6曲のピアノ・ソナタを次々に仕上げている。
作品10の3曲は、それぞれが際立った内容を特徴とする。「第5番」「第6番」が3楽章と小規模な作品が続いたが、3曲目の「第7番」は4つの楽章を擁する大きい規模で書かれ、内容もより一層深いものが展開する。第2主題からは、木管的な響きが聴こえてきます。第66小節あたりからは、楽器が次から次へと変わっていく様子が浮かんできます。
現代のピアノより音域の狭い当時のピアノでは出せない音も出てくる。「第7番」は明らかに、「オーケストラ」が意識されています。ベートーヴェンの頭の中では、オーケストラの多様な音が響いていたようです。
この曲に先駆けて、「4手のためのピアノ・ソナタ ニ長調」を作曲しています。この作品は、4手連弾、つまり2人で弾くために書かれました。リヒノウスキー侯邸での室内演奏会で、どこぞの貴婦人と共演することになったのでしょうか。ベートーヴェンの創作力に加勢したのではないかしら。初期の傑作ソナタとなる《悲愴ソナタ》作品13や作品14-1までの6曲のピアノ・ソナタを次々に仕上げる原動力として、作品の傾向を探るように、Op.6から作曲順にピアノ・ソナタを聴いてみるのも面白いかもしれません。その先に《月光ソナタ》が待ち構えるのです。
2020年10月07日
2020年10月06日
2020年10月05日
ベートーヴェンは日記や書簡で「愛する人」と呼んでいますから、4番のソナタは非常に愛情の込もった作品になっています。

ベートーヴェンのピアノ・ソナタ19番、20番が第1番よりも若いときの作曲でしたが、今日のピアノ・ソナタ第4番と今では整理されている作品は、作曲された順番に並べると、第5番と第6番の間に位置します。
アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ
カール・ツェルニーは「熱情」と愛称で呼ばれるべきは第23番ではなくこのソナタではないかと述べている。ベートーヴェンの全32曲のピアノソナタの中でも第29番(ハンマークラヴィーア)に次ぐ大作です。
クラウディオ・アラウ
長さの面では大作ですが、ベートーヴェンはこの作品のことを日記や書簡で「Die Verliebte(愛する人)」と呼んでいますから、非常に愛情の込もった作品になっている。
ダニエル・バレンボイム
ベートーヴェンのソナタに抱く、一般的なスタイルです。
ヴァレンティーナ・リシッツァ
このソナタはベートーヴェンの弟子であるバベッテ(バルバラ)・フォン・ケグレヴィッチ伯爵令嬢(1780~1813)に献呈されており、この曲のもつ長大さや、求められるテクニックからバベッテが相当なピアノの名手だったことがわかるもの。「不滅の恋人」(のちにベートーヴェンの手紙に現れる名前がわからない女性)の候補ではないそうですが、ベートーヴェンが彼女の才能に惚れこみ、認めていたのは確かなようです。
スヴャトスラフ・リヒテル
強弱自在ながら、アクロバティックなところの微塵も感じさせない、大人のベートーヴェンです。
2020年10月04日
音楽の歴史の中に一つの革命的な端緒を開いた《熱情》の中にあるベートーヴェンの驚くべき綿密な思考を聴き比べる。

ベートーヴェンのピアノ・ソナタには「愛称」が付けられているものがたくさんありますが、彼自身が名付けたものは《悲愴》ソナタだけだと言われています。「ベートーヴェンの三大ピアノ・ソナタ」に数えられるこの《熱情》も本人が名付けたものではありませんでした。
ヴァレンティーナ・リシッツァ
ピアノ曲に限ったことではないが、「愛称」を曲名と思い込んでしまうと、誤った作品イメージを描いてしまうかもしれない。場合によっては、演奏解釈にまで影響を与えてしまうだろう。
クラウディオ・アラウ
《熱情》の由来もベートーヴェン死後10年以上を経た1838年にハンブルクの音楽出版社クランツから出版された、「4手連弾版によるベートーヴェンのヘ短調ソナタ」の表紙に印刷されたSonata appassionata が初出で、以後オリジナルのOp57も《アパッショナータ(=熱情)》と呼ばれるようになった。
ダニエル・バレンボイム
ベートーヴェンのソナタに抱く、一般的なスタイルです。
ウラディーミル・アシュケナージ
これまでに楽想の対比ということでは、同じ旋律或いは同じ動機を、piano やforte で 表すことは多々あっても、ppやffで提示することはありませんでした。そして、第一楽章の終結では音楽はdiminuendoとなり、最後にはppp の表示がベートーヴェンによって書かれていることは特筆すべきことです。疾風怒濤の感情の嵐、情熱の奔流の終楽章では、その当時のピアノという楽器の概念などを度外視して、狂暴なまでの感情の爆発に終始します。
楽想を形成する一つひとつの動機、その構成、配置に至るまで、そこにはベートーヴェンの驚くべき綿密な思考があったことを、後世の数々のベートーヴェン研究家達が指摘しています。
ベートーヴェンの音楽には、ソナタ形式という原理のなかに、それまでになかった葛藤に満ちた、攻撃的で破壊的な力が入ることを許し、いわば音楽の歴史の中に一つの革命的な端緒を開いた。そして、最後のコーダでは、実に10回にわたり楽器の最高音を叩き、その後、凄まじい奔流となってピアノの最低音の奈落の底まで、聞く人の心を引きずり込むようです。
楽想を形成する一つひとつの動機、その構成、配置に至るまで、そこにはベートーヴェンの驚くべき綿密な思考があったことを、後世の数々のベートーヴェン研究家達が指摘しています。
ベートーヴェンの音楽には、ソナタ形式という原理のなかに、それまでになかった葛藤に満ちた、攻撃的で破壊的な力が入ることを許し、いわば音楽の歴史の中に一つの革命的な端緒を開いた。そして、最後のコーダでは、実に10回にわたり楽器の最高音を叩き、その後、凄まじい奔流となってピアノの最低音の奈落の底まで、聞く人の心を引きずり込むようです。
ウラディミール・ホロヴィッツ
ベートーヴェンのソナタを弾いていることより、ピアノ音楽の大傑作のファンタジーが羽ばたいていく。
マレイ・ペライア
幻想的なムードをまとった、大人のベートーヴェンです。
2020年10月03日
友人を思い出しながら作曲、、、「暁」という名がふさわしいベートーヴェンのピアノ・ソナタの超大作をを聴き比べる。

クラウディオ・アラウ
リズムとテンポが刻まれているところに、シューベルトの歌謡性とは違うグレン・グールドの鼻歌のようなフレーズが絡む。クラウディオ・アラウの演奏からは、映像が浮かんでくる。スリリングなものでも、推進するものでもない。アームチェア・ディテクティブで語られるような音楽だ。
ヴァレンティーナ・リシッツァ
ヴァレンティーナ・リシッツァの演奏はリズムを正確に守って、右手の旋律が添えられています。ベートーヴェンがクラシック音楽に持ち込んだ斬新な試みは《リズム》だと言うことは、最近クローズアップして説明される勘所です。この《ヴァルトシュタイン》ソナタから新しいピアノ音楽がスタートしたとも言われていること、シューベルトが影響を受けているのがよく感じ取れます。
ウラディーミル・アシュケナージ
通常「ワルトシュタイン・ソナタ」と呼ばれることの多いこの曲は、最終第3楽章のパッセージが、まばゆい太陽が朝上ってゆく様子にたとえられて、「オーロール(暁の)・ソナタ」とフランスやロシアで呼ばれています。難聴という音楽家にとって致命的な病気を乗り越えたベートーヴェンにとっても、ピアノ音楽にとってもこの曲は「暁」という名がふさわしいといえましょう。ロシア系ピアニストの演奏からは、この「暁」が感じられまる共通性がありますが、アシュケナージの演奏をその参考とします。
エミール・ギレリス
鋼鉄のタッチと通称される完璧なテクニックに加えて甘さを控えた格調高い演奏設計で非常に評価が高いピアニスト、ギレリスの古典的解釈のベートーヴェンです。バロック時代のスカルラッティやバッハ、ロマン派のシューマンやブラームス、さらにはドビュッシーやバルトーク、プロコフィエフといった20世紀音楽に至るまで幅広いレパートリーを持っていた。プロコフィエフからはピアノ・ソナタ第8番を献呈され、1944年12月29日にはこの作品を初演してもいる。とりわけベートーヴェンの解釈と演奏においては、骨太で男性的な演奏で「ミスター・ベートーヴェン」と呼ばれるほどであった。ドイツ・グラモフォンレーベルにベートーヴェンのピアノ・ソナタの録音が進行中に死去しました。
アニー・フィッシャー
溌溂とした表現力と細部にわたる集中力で圧倒されるアニー・フィッシャーのベートーヴェン。戦後はブダペスト中心に活動したため、ほぼヨーロッパのみでしか演奏に触れられなかったにもかかわらず世界的に評価が高いピアニストのひとりです。戦中・戦後通しての王道、ベートーヴェンはこうでなくてはと自信に輝いている。ハンガリー生まれの名女流ピアニストで、8歳でベートーヴェンのピアノ協奏曲第1番を演奏したと伝えられている。リストに系譜が引き継がれたことを実感する、フィッシャーのベートーヴェンは造形が大きく、感傷性や曖昧さのかけらもありません。テンポは早目で、聴き手の気持ちを煽るようなボルテージの高さが独特。有名な『悲愴』『月光』『熱情』など、はじめて聴く作品のような新鮮さに満ち、また緩徐楽章での語り口の巧さに引き込まれます。正統派でありながら、こんなベートーヴェンは絶対に聴けません。
1923年にフランツ・リスト音楽院に入学し、アルノルド・セーケイとエルンスト・フォン・ドホナーニより受け継いだ知的な解釈に加えて、男性的な力強さにも不足しないフィッシャーの持ち味が、ここでは見事に結実しています。「ウィンナートーン」と呼ばれるベーゼンドルファーの深みある響きも、彼女の解釈に相応しい効果を上げており魅力的。
1923年にフランツ・リスト音楽院に入学し、アルノルド・セーケイとエルンスト・フォン・ドホナーニより受け継いだ知的な解釈に加えて、男性的な力強さにも不足しないフィッシャーの持ち味が、ここでは見事に結実しています。「ウィンナートーン」と呼ばれるベーゼンドルファーの深みある響きも、彼女の解釈に相応しい効果を上げており魅力的。
ダニエル・バレンボイム
ベートーヴェンのソナタに抱く、一般的なスタイルです。
アルフレッド・ブレンデル
幻想的なムードをまとった、大人のベートーヴェンです。
2020年10月02日
「七重奏曲」でも使っていたベートーヴェンお気に入りの主題が出てくる、やさしいソナタを聴き比べる

ヴァレンティーナ・リシッツァ
昨日の19番の演奏をふまえて、20番はヴァレンティーナ・リシッツァの演奏から聞きましょう。
ダニエル・バレンボイム
昨日の19番と同じベクトルでバレンボイムは演奏をしています。ベートーヴェンのソナタに抱く、一般的なスタイルです。
エミール・ギレリス
鋼鉄のタッチと通称される完璧なテクニックに加えて甘さを控えた格調高い演奏設計で非常に評価が高いピアニスト、ギレリスの古典的解釈のベートーヴェンです。バロック時代のスカルラッティやバッハ、ロマン派のシューマンやブラームス、さらにはドビュッシーやバルトーク、プロコフィエフといった20世紀音楽に至るまで幅広いレパートリーを持っていた。プロコフィエフからはピアノソナタ第8番を献呈され、1944年12月29日にはこの作品を初演してもいる。とりわけベートーヴェンの解釈と演奏においては、骨太で男性的な演奏で「ミスター・ベートーヴェン」と呼ばれるほどであった。ドイツ・グラモフォンレーベルにベートーヴェンのピアノソナタの録音が進行中に死去しました。
アニー・フィッシャー
溌溂とした表現力と細部にわたる集中力で圧倒されるアニー・フィッシャーのベートーヴェン。戦後はブダペスト中心に活動したため、ほぼヨーロッパのみでしか演奏に触れられなかったにもかかわらず世界的に評価が高いピアニストのひとりです。戦中・戦後通しての王道、ベートーヴェンはこうでなくてはと自信に輝いている。ハンガリー生まれの名女流ピアニストで、8歳でベートーヴェンのピアノ協奏曲第1番を演奏したと伝えられている。リストに系譜が引き継がれたことを実感する、フィッシャーのベートーヴェンは造形が大きく、感傷性や曖昧さのかけらもありません。テンポは早目で、聴き手の気持ちを煽るようなボルテージの高さが独特。有名な『悲愴』『月光』『熱情』など、はじめて聴く作品のような新鮮さに満ち、また緩徐楽章での語り口の巧さに引き込まれます。正統派でありながら、こんなベートーヴェンは絶対に聴けません。
1923年にフランツ・リスト音楽院に入学し、アルノルド・セーケイとエルンスト・フォン・ドホナーニより受け継いだ知的な解釈に加えて、男性的な力強さにも不足しないフィッシャーの持ち味が、ここでは見事に結実しています。「ウィンナートーン」と呼ばれるベーゼンドルファーの深みある響きも、彼女の解釈に相応しい効果を上げており魅力的。
1923年にフランツ・リスト音楽院に入学し、アルノルド・セーケイとエルンスト・フォン・ドホナーニより受け継いだ知的な解釈に加えて、男性的な力強さにも不足しないフィッシャーの持ち味が、ここでは見事に結実しています。「ウィンナートーン」と呼ばれるベーゼンドルファーの深みある響きも、彼女の解釈に相応しい効果を上げており魅力的。
アルフレッド・ブレンデル
幻想的なムードをまとった、大人のベートーヴェンです。